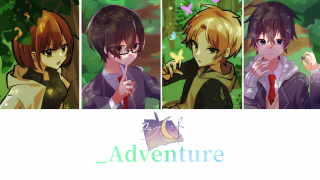呼ばれた、気がした。
どこからともなく吹いてくる風に、おれは振り向く。声の主を探して。
「……あれ……?」
おれはなんだか拍子抜けした。そこにはユウトがいて、まっすぐ目が合う。ユウトの声ではなかったと思うけど、近くには他に誰もいない。気のせいだったのかな。
ユウトはおれの双子の弟だ。ユウトがメガネの奥の瞳をまわりへ向けたので、おれもならって辺りを見渡した。
そして……。
「ねえユウト。ここどこだろう」
「さぁ」
鬱蒼としげる木々が、ぐるりと見渡す限りどこまでも続いている。おれたちは、深い森の中にいるみたいだ。頭上からは、太陽の光が木々の葉をすかしてまぶしく降り注いでいる。
「うーん? あれ、うーん。夢かなぁ」
もちろん、こんな場所にやってきた覚えはない。そもそも今まで、なにをしていたっけ? なんだかぼんやりとして思い出せない。首を傾げて「夢だ」、そう結論を出したところ、ユウトがおもむろに手を伸ばしておれのほっぺを引っ張った。
「なにふんだよ!いへえよっ!」
「夢じゃなさそうだな」
おれの抗議の声も無視して、ユウトはそんな風にいってのける。自分のほっぺでためせっての!
うらみを込めてじーっと見つめる先で、ユウトは一歩踏み出した。
「とりあえず、近くを歩いてみるか」
「うーん、そうだね――って……いやちょっと待ってよ、冷静過ぎない!?」
頷きかけたおれのなかで突然、現実がバクハツした。ここはどこ? 知らない森。さっきまでなにしてたっけ? 思い出せない。夢じゃない、なさそう。ユウトがあまりにも冷静過ぎてめちゃくちゃ普通に受け入れそうになったけど。
とんでもない状況じゃん。危ない危ない。
「混乱してどうにかなるわけじゃないだろ、時間の無駄だ」
ユウトはさらっとそんなことを言うので、おれは感心してしまった。
「はぁ~、すごい、冷静すぎてすごい」
まあ、ユウトが焦ったり動揺したりするのは、これまでの人生でも数えるほどしか見たことがない。そんなユウトがいれば、慌てるのもばからしく思えてきて、なんだか安心してしまうのだ。うーん、おれも大概かもしれない……。
「ほら、行くぞ」
「わかった、行ってみよう!」
……って言っても。
360度、どこまでも、森、森、森。目印になりそうなものも、変わったものも目につかない。
どっちへいけばいいんだろう?
風が木々の間を吹き抜け、静かな森を揺らした。
◇
ユウトが空を見上げて、太陽を目印に森を進んでいくのについていく。
「うーん……制服を着てるってことは、学校に行ったってことだよね……ユウトは何かおぼえてる?」
「いや、何も思い出せない。気がついたらここにいた」
「だよなあ、おれも同じ」
せめてもと、わずかな情報を整理してみる。おれもユウトも、通っている高校の制服を着ている。けど、荷物は持っていなかった。だから鞄に入れていた携帯電話も手元にはなく、現在地や地図を調べることもできない。
おれが制服の他に身に着けているのは……このイヤホンくらいだった。おれはうまれつき耳が良い。というか、良すぎて、周囲の音に疲れてしまう。なので、いつもこうしてイヤホンをしているのだ。
そのイヤホンのワイヤーをたどって、ポケットの中からレコーダーを取り出した。古びたICレコーダーだ。握りしめると手になじむ。おれが肌身離さず持っているのはこれだけ。ユウトは……メガネくらい?
「でも、これなくさなくてよかった!」
「別に役に立たないだろ、それは」
ユウトがちらりと振り向いて、おれが手にしたレコーダーを見ると微妙な顔をした。
「役に立つとか立たないとかじゃないだろ? 大事なんだから」
「そんなこと言ってる場合か」
まあ確かに、この現状を解決できるような代物ではないのは事実だった。他にポケットの中を探してみるが、三日前のレシートが入っているだけ。このまま森を抜けられなければ、どうなるんだろう。もうだいぶ歩いたような気がする。
「何もないや。はあ、このまま野宿かあ」
「最悪、飢え死ぬだろうな」
「怖いこと言わないでよ!」
歩き続けていると、じわじわと不安が現実的になってくる。遭難した時は……動かない方がいいんだっけ? 川でも見つければ水は飲めるだろうか? いや……きれいに見える水も菌とかで危険なんだっけ。だめだ。サバイバルの知識がまったくない。ユウトは物知りだし、おれよりは知っているかもしれない。
「ねえ、ユウト――どわっ!?」
鼻をぶつけた。
「なんで急にとま――」
「静かにしろ」

ユウトが立ち止まって周囲を伺っている。
「何か聞こえないか?」
「……え?」
おれは耳を澄ました。確かに聞こえた。駆けている、生き物の足音みたいだ。おれはイヤホンを外した。
「……!」
聴覚空間がぐんと広がり、森の息吹が渦巻いて耳に届く。おれはなにかがいつもと違う事に気づきながら、ユウトの腕をつかむと走り出す。
「どうした?」
「き、聞こえるんだ……逃げなきゃ!」
説明する余裕がない。察したのかユウトはそれ以上何も言わずに前へ走り出て、おれを引っ張って森を駆けだす。ユウトの方が足が速かった。木々の間を抜けて、転げ落ちそうになりながら傾斜を滑り降りる。
「な、なんだこれ……ッ!」
頭が痛くなりそうなほど、うるさい。思わず耳をふさぎたくなるがその暇もない。まるで騒がしい雑踏か道路の中心にでもいるみたいだ。ここにはおれ達以外に誰もいないのに、この溢れる「声」はなんだ?
一つ一つは聞き取れない、さんざめく話し声、笑い声。吹き過ぎる風が混ぜ返す。そしておれたちを明らかに追いかけてくる、異質な足音。牙の間から漏れる唸り声。
『――喰ってやる』
「――ッ!」
その時足がもつれ、石につまずくとおれはものすごい勢いで転んだ。ユウトも巻き込んで坂道を転げ落ち、おれたちはそのまま藪に突っ込んだ。
「いッてて……!」
「大丈夫か?」
「ごめん、ユウト……」
ユウトは素早く体勢を立て直し、おれを引っ張り起そうとした。そこで、おれの右足に激痛が走る。くじいてしまったみたいだ。
「た、立てない……」
ユウトは後ろを振り向いた。おれも息をきらしながら目を向ける。
既に追いつかれていた。そこには、一匹の異形の獣がいた。
オオカミ――に似ていても、こんなオオカミがこの世にいるはずないことくらいわかる。馬ほどもの背丈があった。その顎から鋭い牙が覗き、唾液が滴る。紅い両眼がおれたちを獲物として見下ろしている。
「こ、こわぁ……」
おれは思わず呟いた。ユウトは目を離さない。にらみ合う、数秒間。音が溢れる。めまいがしてくる。
ああ、これは一巻の終わりだ。おれはユウトの手首をぎゅっとつかんだ。
「……大丈夫だ」
「……ユウト」
その声を聴いた瞬間、あれほどうるさく、ごちゃまぜだった周囲の音がすうっと静まった。
ただ静かな世界で、鼓動だけが聞こえる。
おれは目を閉じ、聴覚に意識を集中する。これまでずっと、そうしてきたように。
『人間の子――、祈りなさい』
……祈る?
やわらかく、優しい声。おれは目を開ける。傍らに、小さな白い花が咲いていた。はなびらがやわらかく、揺れる。
『祈りなさい、守るべきもののために』
息を呑んだ。
獣が身をかまえ、今にもおれたちにとびかかろうとする。ユウトはおれを庇うように立った。その背中を見上げ、おれは心に満ちる不思議な力を感じた。
手のひらを前に向ける。そして、……祈る。絶対におれを置いていったりしない、ユウトのために。
おれは、――守りたい!
手のひらから、白く輝く光が溢れる。それは流星のようにユウトの横をかすめて獣のほうへ飛んだ。次々と獣の体にぶつかると、獣は吠えて飛びのいた。
「――な……」
ユウトがさすがに驚いた顔でおれの方を振り向いた。おれも自分の手のひらをみつめてぽかんとする。――なに、今の?
「な、な……?」
「逃げるぞ!」
ユウトは瞬時に我に返って、おれを力強く引っ張り上げた。痛む足をかばって、なんとか立ち上がる。でも、とうてい走り出せそうにはない。獣は体勢を立て直そうとしている。
おれはユウトの手を振り払おうとした。――ユウトだけでも、ここから逃げて、そう口を開きかけた時。
「――ちょっと待ったあ――!」
よく通る声が、木々の隙間から響き渡った。
それは、知っている声だ。おれたちは一瞬、顔を見合わせた。
脇の小道から、一人のお姉さんが走り込んできた。頭に葉っぱを載せている。
「……カオルさん!?」
無謀にもおれたちと獣の間に割り込んで立ちはだかるのは、おれたちの従姉の、カオルさんだった。――でもなんで、カオルさんがここに?
「ユウヤくんたちに何かしたら、この私が許さないんだからね!」
と、巨大な獣に向かって怒鳴った。獣もさすがに引いている。
「さ、さすがカオルさん、度胸がすごすぎる……」
「一体どうなってんだ……」
なにがなんだか分からない。ユウトは一周回って呆れている。うん、気持ちはわかる。
「……で、どうするんだ?」
とユウトが呟くと、沈黙が下りた。しばらくして、カオルさんがこちらを振り向く。
「……どうしよ?」
「どうしようもないの!?」
思わずツッコんでしまった。カオルさんは気まずそうに頬をかいた。
「あはは~……」
流石に気を取り直した獣が、今度こそおれたちを仕留めようと低く唸った。
ああ、今度こそ絶体絶命。
おれは天を仰いだ。
――「始まりに耳を澄まして」フラグメント_Adventure
chain story