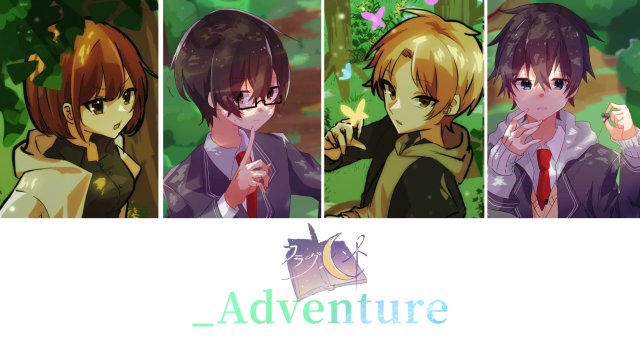俺たちは久しぶりに王都を訪れ、往来を歩いていた。とくに用事があったわけではなく、なんとなく近くまで来たついでだ。
道端の露店から漂う油の匂いの中、悪趣味なネオン看板を眺めながら歩いていると、イルがふと喋るのをやめて首を傾げた。
「なーんか人が少なくないか?」
「……確かに」
王都は魔界の中心地だ。様々な種族たちが行き交い、常に煩いほどにぎわっている。だが今日は人通りがまばらだ。真っ先に思い当たるのは例の噂だった。
「そういえば《扉》が開いたっていう……あれのせいじゃないか?」
「あー、ゼータが開けたとかっていう?」
俺は頷いた。
ゼータ……魔王になって以来この魔界を闇雲に荒らしている迷惑なやつで、基本的には近づきたくない。
そのゼータが、魔界に発見されていた旧時代の遺跡を調べて、それがどこか別の場所へ繋がる《扉》であることを解明した。詳しくは知らないが、とにかくその扉は開かれて、魔王軍の大半がその別の世界とやらへ移動しているという話は聞いていた。
「やっぱりみんなその扉の向こうへ行っちゃったのか~」
「そうみたいだな」
「ん~……」
と宙を見つめて考え込んだイルがきらりと目を光らせたので、当然俺は嫌な予感がする。
「なぁオレたちも今から行ってみないか? 扉の向こう! 誰でもいけるんだろ?」
予想通りだった。
「……だいたいその扉ってのはどこにあるんだよ」
「たしか東の方のデカい山だろ? 行けば分かるって! な?」
「……山って……アルケア山か」
「あー多分それ!」
別の世界……というのは確かに、興味がないこともない。どんな世界だか知らないが……。
特に目的もない日々だし、この先の予定があるわけでもない。だが、向こうに行った面倒な魔王軍の連中に遭遇するかもしれないし、危険もあるかもしれない。
「せめてもう少し調べてからにしないか」
「え〜面倒だろ、行ってみようぜ!」
イルはいつも無鉄砲に突っ込んでは痛い目を見ているのに、なぜ学ばないのか甚だ疑問だ。
「あのなぁ……」
「大丈夫だろ〜? オレたちなら!」
まぁ、それは……と言葉を呑み込んで尚も続けかけた俺の手を掴んでイルは空へ飛び上がる。
「行こうぜ!」
「……はぁ、東はあっちだろ」
「あれ?」
結局押し切られる俺も俺だな、と思いながら。
魔界の端の方へ行くと、頭上の闇の向こうに、次第に赤黒い岩肌が見えてくる。
東端には、高く伸びて上端が天井まで繋がっている巨大な山、アルケア山があった。
「見ろよルナ、なんか街ができてるなー、あそこ」
「だな」
このあたりには以前なにもなかったはずだが、山から少し離れたところには街の明かりがちらついている。ところどころの青い光が灯っているのを見るに、主に魔王軍の拠点となっている街のようだ。
「あまり近づかないほうが良さそうだ」
「そうだなー」
魔王軍の連中はやたらと俺達に絡んでくる。以前に魔王軍の吸血鬼と戦った時に聞いた話では、ゼータが俺たちを魔王軍に引き入れたがっているという話だ。それは御免被りたいところだが、ゼータ本人や幹部クラスの連中に遭遇すれば流石に俺たちも敵わない。魔王軍にはなるべく関わらないのが賢明だった。
「てか、扉の方はほんとにいけるんだろうな?」
「さぁ……お前が言ったんだろ、誰でも行けるって」
「んー、オレが聞いた話ではな?」
もしかしたら魔王軍が仕切っていて、勝手に出入りはできないかもしれない。それならそれでいいか、と俺は思いながら山へ近づいていった。
赤黒い岩だらけの山道をたどりながら昇っていくと、やがて山の内側へ続く洞窟か何かの石扉が見えてくる。
「ふーん、この中みたいだな」
その扉は開かれていて、内部に石畳の床が真っすぐ伸びている。
壁には松明が並び、奥の闇を薄っすらと照らしていた。
「あんまり人もいないな」
「だなー、扉を開けたってのも結構前みたいだし」
俺達は並んでその扉を通り抜けると長い廊下を歩いた。
反響する足音に包まれて、火の横を通るたびに俺達の影が浮かんでは過ぎていく。
「あー……おっ、響くなぁ〜ここ」
イルは変な声を出しては響かせて遊んでいる。
「ガキかよ……」
「あ! 向こうが開けてる」
イルの指差す通り、道の突き当りに広い空間があるのがぼんやりと見えていた。
駆け出していくイルを呼び止める気にもならない。
先にそこまでたどり着いたイルが覗き込んで上を見上げた。
「お、階段がある」
「どこまで続いてるんだ? もうだいぶ……」
ふと俺は振り向いて、来た道が塗りつぶされたような暗闇なのに気づいて息を呑んだ。
ここまで歩く間、ずっと壁に松明があったはずなのに。
「どうかしたか? ルナ」
その声に我に返った瞬間、気づけば廊下は元のように灯りにぼんやりと照らされていた。
……気の所為、だったのか?
「いや……」
俺はかぶりを振って、再び前に進む。何度か背後を振り返るが、もう特に変わった様子はなかった。
突き当りは丸い広間につながっていた。頭上は吹き抜けて、薄暗い闇にぼかされて天井は見えない。壁を取り巻くように螺旋階段が伸びている。
「飛んでいくか?」
と顎で上を示して尋ねるとイルは「いや」と階段に足をかけた。
「昇ってこうぜ」
「はぁ? 面倒だろ」
「いいからいいから!」
なぜかイルは階段を昇りたいらしい。仕方がないので俺もそれに従った。
階段を昇る二つの足音が冷たく響き渡る。
上へ行くほど、空気はどこか淀んでいくのを感じた。
「にしてもさ〜、別の世界ってどんなとこなんだろうな?」
「さぁ……」
「何か、噂じゃー俺達みたいなやつらが住んでるらしいな」
「人なのか?」
「んー、多分」
階段は続いていく。
「魔王軍は何をしてるんだろうな」
「ゼータのことだからなぁ〜、どうせ向こうの世界もめちゃくちゃにするんだろ?」
「だろうな。あいつの行動は理解できない」
「だなー、オレあいつ嫌いだよ」
松明が火花を散らす。ぐるぐると、螺旋を昇り続ける。
「いつかオレたちもっと強くなって、あいつらとも戦ってみたいなー」
「ゼータ達か?」
「いつまでもあいつらを気にするのも癪だろ?」
「まぁ……」
「ルナとオレなら最強になれるって!」
「お前はまずその自惚れと油断をなんとかしろ」
「……はーい」
そんな風に他愛ないことを話していた。階段は長い。イルはふと上下左右をきょろきょろと見回し、視線を上へ向けたまま呟いた。
「なぁルナ、もしもさぁ……」
それから少し間が空いた。
「なんだ?」
「んー……オレと他の何かを選ばなきゃいけなくなったらどうする?」
「なんだよ、他の何かって」
「えー、そうだな〜、世界とか!」
急に勢いよく指を立てて言うイルを、呆れた目で見やる。
「なんだそれ。そんな馬鹿げた話があるか」
「もしもだろ〜? もしも」
世界などと言われても、漠然としすぎて考えようもなかった。肩を竦め、冗談めかして「そりゃ世界だろ」と言うと、イルはニヤニヤしながら俺をつつく。
「ほんとかー?」
「当たり前だろ。一人のために世界を滅ぼすバカがどこにいる」
「でも実際そうだよなー。だってオレのために世界が犠牲になるなんて、後味悪いもん」
「だろうな」
馬鹿げた話だとわかっていながら、お前はどうなんだよ、と何となく尋ねかけた時、気づけば階段の終わりにたどり着いていた。
「おっ! やっと上までついたみたいだな〜」
「ああ……ずいぶん昇ったな」
横壁に道が続いている。その先には、とてつもなく広いドーム状の空間が開けていた。
「うわ、広いなぁ!」
見慣れない、青白い石材でつくられた美しい広間だった。天井の中央はキラキラと光りを透かして輝き、青や緑の光の筋が溢れて、広間の中心を照らしている。
「あれが扉なんじゃないか?」
イルが指差す先、光に照らされて、巨大なひし形の枠のようなものが浮かんでいた。大きな額縁のようで、その内側には暗い虚無が満たされている。
「へぇ……あれをくぐればいいわけか」
近寄ってみると、その《扉》は背丈の三倍ほどの高さがあった。
内側の暗闇を覗き込んで目を凝らしても、なにも見えない。
「本当に大丈夫なんだろうな」
「大丈夫だろ、多分」
「多分って……」
「行ってみようぜ!」
「あ、おい……!」
イルは俺の手首を掴んで引っ張ると、深い闇の中へ飛び込んだ。
不思議な感覚だった。
身体と精神が、ねじれて歪むような。奇妙な浮遊感覚が身体を包み、でもそれは一瞬だった。
「……!」
最初に感じたのは風の音、そして水の匂いだった。
暴風と冷たい水がふきつけてくる。隣でイルが小さく声を上げるのが聞こえ、俺は目を開ける。
「なんだこの水……」
バケツでもひっくり返したみたいに、上から降り注いでくる。俺は顔を上げた。そして息を呑む。
そこは魔界とは違って明るく、そして高い。天井……なのか、黒いもやのようなものが一面を覆っている。
「ん? これは……《海》……?」
と呟きながら、イルが一人で駆け出した。
そこはどうやら橋の上だった。左右にどこまでも広がる水……水平線。思わず息を呑んだ。
「ルナ! これ、海じゃないか?」
そう言いながら振り返ったイルに言葉を返そうとした時、異変を直観した。視界の端で、海が青く輝いた。――光が海面を舐めるように迫ってくる。理由もわからないのに、原始的な恐怖に身がすくむ。
「――!? 戻ってこい、イル!」
俺は駆け出す。え? と不思議そうな顔をしたイルが顔を上げる。黒い靄の切れ間から差した光は、ついに橋の上のイルを照らした。その瞳が光を反射し、ぎらっと輝いた。
「――ッ!」
もう遅かった。声にならない悲鳴がイルの喉から漏れる。全身が橙の炎に包まれて燃え上がり、イルは膝から崩れ落ちる。
俺は扉の影を出て、イルに走り寄った。ほんの一瞬、浴びた光に身体が焼ける――熱い。その手を掴んで瞬時に影の中へ引き戻すと、イルを抱えて踵を返し、扉の中に飛び込んだ。
視界が歪み、浮遊感の後に元通り、魔界の扉の広間に戻ってくる。
「あれは……太陽……!?」
呟いた声がかすれた。頭がぐらぐらする。
「ぐ……」
呻き声に慌てて目をやって、俺は床にイルを寝かせた。橙色の炎が蛇のようにのたうって、イルの身体を焼いている。
「待て、今消すから……!」
俺は手のひらから冷水を生成してイルの体を包んだ。ほどなくして炎は収まるが、全身がひどい火傷に傷ついていた。目も開けられないようだった。
「大丈夫か……!?」
「へへ……あのおとぎ話、本当だったみたいだな……」
吸血鬼は太陽の下に出られない……。だがあれはおとぎ話にすぎなかったはずだ。まさか、この扉の向こうにその《太陽》があっただなんて。
「……ッ、そんな事言ってる場合か!」
次に治癒魔術を施して、その傷が全く癒えないことに気づく。
「治癒魔術が効かない……?」
俺はイルを抱き起こして、イルの口元に首筋を近づけた。
「俺の血を飲めるか?」
「ん……」
イルの吐く息が焼けるように熱い。その牙が俺の首筋に触れるが、噛みつくほどの力が入らないらしい。
俺は自分の指先を牙で割いた。血が滴る指先をイルの口の中に入れて、血を飲ませる。
火傷しそうなほどその口の中が熱い。吸血鬼はただでさえ体温が低いのに、ものすごい高熱だった。
後悔が押し寄せる。扉の向こうに“太陽”があった……ならあれは“空”だったのだ。扉の向こうの世界には空があり、太陽があった……それを知っていれば。もう少し調べていれば。
そんな事を考えながらしばらく血を飲ませていたが、傷が癒える気配がない。冷たい汗がこめかみを伝う。こんなことは今までに一度もなかった。どうすればいい? このままじゃ――。
「クソ……!」
「――ッ」
イルは突然咳きみ、顔を逸らして血を吐き出した。量からして明らかにイル自身の血が混じっている。身体の外側だけではなく、体内も損傷しているのだ。
「――ごめん、ルナ……オレ……」
「謝るな」
「はは……、ルナ、そんな顔するなよ、大丈夫だって……がはッ……げほ……」
「……黙ってろ」
俺はイルを抱きかかえる。 猛烈な熱さに歯を食いしばりながら、俺は広間を飛び出し、昇ってきた階段の横を飛び降りていく。だれか治癒師を探さなければ。このままじゃ――。
山際の街にはすぐについた。たちの悪い魔王軍に遭遇する可能性もあったが、今はイルをなんとかしなければならない。
俺は治癒師のいる病院を探して町中を走り回っていた。
「――わ!?」
「悪い……」
曲がり角でぶつかりかけた人影を避けて、走り続けようとした俺の背後から、声が追いかけてくる。
「あれ、ベルナードくん? どうしたの?」
振り向いた俺は、見覚えのある姿に目を見開く。
「ラスティ……!?」
いつものように杖とスーツケースを手にして、そこに立っていたのは、移動喫茶店《ラコルト》の店主、ラスティだった。
ある時偶然知り合って以来、俺たち二人はラスティの店を見かける度に訪れていた。俺たちのことをよく知る数少ない人物だ。
ラスティはすぐに俺の腕の中のイルに気がつくと、血相を変えて駆け寄ってくる。
「アイルーズくん
ちょっと見てもいい? と、ラスティは苦しげに呻くイルの顔や腕を覗き込む。
「ひどい熱傷だ、体が熱い……普通の魔術ではないみたいだね」
「ああ、俺の治癒魔術じゃ効かない……血を飲ませても効果がないんだ」
言いながら息が切れる。
「落ち着いてベルナードくん。この傷はきっと普通の治癒魔術じゃ治せない……ぼくにもっとよく見せてくれる?」
「ああ……治せるか……!?」
「……わからない。とりあえず来て!」
足早に歩きだすラスティを追いかける。
俺の腕の中で、アイルーズは既に意識を失っていた。
「……太陽、か……」
ラスティは空き地でスーツケースを例の店に変えると、俺たちをその中へ入れてくれた。
三人で入るにはやや手狭だが、寝泊まりできる小さな部屋も備え付けられていて、ベッドにイルが寝かされている。
「扉の向こうの太陽の光が、きみ達には毒だったんだね」
「ああ……。太陽なんて……くそ、知ってれば……」
向こうの世界の事を、せめてやはりもう少し調べるべきだった。なぜイルに流されてしまったのか……。などと、今更考えてももう遅かった。
ラスティはイルの傍らに立って顔を覗き込んだ。
「とりあえずこの傷には普通の治癒魔法は効かない……冷やしながらベルナードくんの血を輸血して、これでしばらくは大丈夫そうだけど……」
ラスティによれば、問題は体表の火傷だけではなく、イルの体内で血液が高温になっている事らしい。その高熱を少しでも下げるために魔法によって冷却をしていたが、体温は依然として高いままだ。先程よりは少し落ち着いたようにも見えるものの、息は荒く苦しげで、目を覚ます様子もない。
「……頼む、しばらく面倒を見てくれないか」
「もちろんいいけど……」
「俺は、治す方法を調べる」
「待って」
部屋を出ようとした俺をラスティが呼び止めた。
「ベルナードくん、その前に腕を見せて」
俺は少し躊躇ったが、ラスティの真剣な目に根負けして、腕を差し出した。
「……やっぱり、火傷しちゃってるね」
「大した事ない」
燃えるように熱いアイルーズの身体をずっと抱えていたからだった。引っ込めようとする手をラスティが引き止める。
「いや、この傷もほうっておくだけじゃ治らない。手当するよ」
「……」
触れているだけでここまで焼けるのに、イル自身はどれだけの苦しみの中にいるのか?
ラスティが俺の腕に薬を塗り、包帯を巻いている間、俺はベッドに寝かされたアイルーズの顔を見ていた。
苦しげに目を閉じて、荒い呼吸に胸が上下する。その全身がひどく焼けただれていた。
もし、このまま――。
最悪の未来が頭をよぎって、俺は首を振る。
「この火傷は治癒魔術の効きが悪いから、治るのには時間がかかると思う……これですこしは傷みがひくといいけど」
そう言ううちに手際よく包帯を結び終えてくれる。
「悪いな、ラスティ……しばらくこいつを任せてもいいか」
ラスティは強く頷いた。
「うん。僕も調べてみるよ。太陽と吸血鬼のこと」
俺はラスティに頭を下げ、それから喫茶店を出た。
――だがどうすればいい?
吸血鬼、太陽、あの火傷……。
手がかりも心当たりもない。だが……他の吸血鬼たちなら何か知っているだろうか?
俺は生まれ故郷である、吸血鬼たちの街へ向かう事に決めて空を飛び立った。
俺だったらよかったのに。
俺があいつより先に踏み出していれば。あるいは、もっと気をつけろと注意していれば。
――後悔なんてしてもしかたがない、少なくとも最悪の状況は免れた。まだ生きているし、今ならまだ間に合うかもしれない。あいつを助けるための、手がかりを探さなければならなかった。
吸血鬼の街は北側の果てにひっそりと築かれている。東のアルケア山からはそこそこの距離があった。全力で飛ばすと、輸血して血が足りないせいか酷い頭痛に襲われる。
だがそんなことはどうでも良かった。数時間もそのまま飛び続けて、やっと見覚えのある街が見えてきた時にはほっとした。
だが近づくに従って、その様子がおかしいことに俺はすぐに気づく。
「街が……?」
人気がない、気配が感じられないのだ。その中に下り立って、街が壊滅していることに気づく。
「……まさか魔王軍か?」
俺は弾かれたように駆け出す。見覚えのあるはずの道や建物が、どこもかしこも瓦礫と化している。かつてイルと通った学校も、もう見る影もない。
やがて俺はいつか住んでいた家へたどり着いた。
「母さん……父さん?」
玄関の扉がなくなっている。覗き込んで思わずそう呼びかけるが、そこに誰もいないことには既に気づいていた。
中に入って少し調べてみる。家の中は荒らされてからかなり時間が経っているようだ。この街の場所はあまり人に知られていないから、噂が耳に届くこともなかったのか。
吸血鬼は決して弱い種族ではない。ここで皆殺しにされたというより、魔界中に散り散りになったと考えたかった。
「クソ……何からなにまで……」
俺は壁に拳を打ち付けた。
こんなことをするのはゼータたち魔王軍しかありえない。
だが今はそれよりも、イルの傷を治す方法を探さなければ。――しかしこれではなんの手がかりもない。
頭痛がひどくなってきた。俺はずるずると廊下の壁に肩を擦って屈みこむ。
なぜこんなことになったのか……。俺のせいだ。イルがいつも細かいことを気にせず無茶をするのなんてわかりきったことだったのに。自惚れと油断――、それは俺の方も同じだった。
……こんなところで立ち止まっている場合じゃない。俺はふらつきながら立ち上がる。
イルは太陽のおとぎ話をどこで知ったのか。もしかしたら、イルの家には本かなにかがあるのかもしれない。
イルが祖父と暮らしていた家は俺の家とそう離れていないが、なんだか思っていたよりも近く、すぐについた。その小さな家は壁が一面なくなって、中が野ざらしになっていた。今にも崩れそうにひしゃげている。
壁の残骸をまたいで中に入り、足の折れて傾いた机やボロボロになった棚を探っていると、ふと本と本の間に折りたたまれた紙が挟まっているのに気がつく。
「……手紙?」
それはボロボロになっているが、開いてみると見覚えのある癖の強い字が書かれている。さっとその最初に目を通して、俺は息を呑んだ。
『アイルーズ、ベルナードへ
見ての通り、街は魔王軍にやられた。ラムダっちゅうやつの仕業だ……。最初は戦ったが、何人か殺られちまった。強すぎる。ワシらは街を手放す事にした。みな散り散りに逃げる事になっとる。ベルナードの両親も今のところ無事だ、安心せい。お前らもラムダには気をつけろ。さてお前らが戻ってきたっちゅうことは、何か困った事があったわけだ。悪いが自分らでなんとかしろ。ただ、もし太陽なら、地上の大陸に行け、それで――』
手紙はそこで途切れている。気づけば破けそうなほどその手紙を握りしめていた。
「もし太陽なら、地上の大陸……?」
扉の向こう側の事か? この手紙が書かれたのはいつなのだろう。扉の向こうの世界、太陽と地上……それをイルの祖父は知っていたのか。
だとすれば、俺はもう一度扉を通って向こうの世界に行かなければならないということか? そこに、イルのあの傷を治す方法があるかもしれない……? だがそれは一体どうやって探せばいいんだ?
俺は手紙を服の中に突っ込んで家を飛び出すと、再び東に向かって空を飛んだ。
「なるほどね、吸血鬼の街が……」
ラスティは言いながら俺の前にカップを置く。カウンターで俺は手紙を広げていた。
「あぁ……吸血鬼達の多くはひとまず無事らしい。それで、イルのじいちゃんの手紙を見つけたんだ。《もし太陽なら、地上の大陸へ行け》……」
ラスティもカウンターの向こうから手紙を覗き込んだ。
「ふむふむ、じゃあ、向こうの世界に手がかりがあるかもしれないってことかな?」
「だとしても……」
俺はズキズキと痛む頭を抑えながら考える。これだけでは、結局ほとんど手がかりがないのと同じだ。何を探せば良いのか、調べれば良いのか? それよりも魔界でイルの祖父を探したほうが早いだろうか。
そんな風に考えている俺の顔をラスティが覗き込んできた。
「……まぁベルナードくん、少し休みなよ」
「……」
「一杯だけでも、ね? ほら、冷めないうちに」
「……そうだな」
俺はカップを手に取った。覗き込むと琥珀色の水面が揺れて、柑橘の香りがふわっと漂ってくる。
いつものようなコーヒーではないらしい。
「蜂蜜入りだから、少しは落ち着くんじゃないかな」
「へぇ……」
舌触りは柔らかく甘い。俺は息をつく。身体が暖まって、張り詰めた感覚が少し解けた。
しばらく沈黙がおりて、俺は少しずつ頭痛が緩んでいくのを感じて目を閉じる。
「……ラスティは最近この街にいるのか?」
「そうだね。扉が開いて以来、ここが賑わってるからさ。というより、他の街はどこも人が減っちゃったしね」
「そうだな……」
「ゼータたち……魔王軍は扉の向こう側の世界を侵略してるんだ。向こうに住んでた人たちもたくさん殺されてる」
少しだけ見た、扉の向こうの世界を思い出した。高い空と広大な海。灰色に曇っていた水平線……。どんな奴らが暮らしていたか知らないが、突然それを壊されることになった人たちが不憫ではある。
いや、向こうの者たちからしたら、俺たちも含めて、みな《向こう側の世界から来た侵略者》だ……。
目を開けると、店先の照明が沁みる。空……雲の切れ間から差し込んだ光が脳裏に閃く。
立ち寄る他の客にラスティがいらっしゃいませ! と明るく声をかけるのがどこか遠く聞こえる。
俺は立ち上がった。
「イルに会ってもいいか?」
「もちろん。向こうから入ってね」
俺は代金を机に置いて店を回り込んだ。
後ろ側から小さな部屋に入る。冷気が部屋を満たしていた。ベッドではイルが寝息を立てていた。苦しそうな息づかいに俺まで苦しくなる。
「イル……」
俺はその傍らに座り込んで、横顔を見つめる。綺麗だった白い肌が今は熱で傷ついていた。
「ごめんな……」
俺が小さく呟くと、「ルナ……?」と唇が震えた。
「イル?」
「だいじょーぶだって、泣くなよ……」
「泣いてない」
こんな時にふざけやがって……。
「水は飲めるか?」
尋ねるとイルは頷いたので、俺は脇に置いてあった水差しを手にとってイルの口元に傾ける。
細い喉が上下するのを見守って、口元を拭ってやる。ふー……と息をついてから、イルは口を開いた。
「……心配、すんなって。オレが……ルナを、……はぁ……、おいてくわけ……ねぇだろ?」
返す言葉が詰まってなにも言えなくなる。
「……そうだな」
やっとの思いでそう言うと、イルは小さく笑った。
「信じて、ないなー……?」
「お前は信用できないんだよ」
「ルナは……疑り深すぎ、なんだよ」
だが結局はそれでも足りないくらいだった。もっと慎重に行動していればこうはならなかったはずだ。俺は俯いて呟く。
「……悪かった。俺が、助けるから、必ず、だから……」
その先が言えずにいると、頭に何かがふと触れた。
顔を上げると、イルが俺に手を伸ばしている。
「あー……触ったら、熱い、かな……」
「……いや、いい」
イルは俺の頭を撫で、その手が頬を滑り落ちてシーツの上に落ちる。
「……ごめん、ルナ……」
「謝るなって……」
俺はその手を握りしめて、どこか懇願するように呟いていた。
気づいたら、そのまま眠っていた。朦朧と夢を見た。光が影を焼いて迫ってくる。巨大な空が視界を満たしている。俺たちを押しつぶそうとする……。
手が燃えるように熱い……ハッと目を覚ますと、イルの手を握りしめていた俺の手のひらが焼けたように熱を持っていた。
そっと手を離し、真っ赤になった手のひらを見つめる。どれくらい寝てしまったのか……。おかげで、頭痛は随分ましになっていた。
ちらりと目をやると、イルは眠っている。俺はしばらくその顔を眺めて、静かに立ち上がった。
「……イル、必ず戻って来る。お前は俺が助ける」
小さく告げて、俺はイルに背を向けると部屋を出た。
店の表に回ると、ラスティはちょうど店じまいをしているところだった。
「……行くの?」
俺に気がついて、ラスティは顔を上げる。
「ああ……大陸に行ってみる」
「まぁ、そうだよね。引き止めても無駄そうだなぁ」
ラスティはそう言って苦笑した。
「その前に、とりあえずぼくが知っていることは全部教えてあげる。向こうの世界のこととか、魔王軍のこと。ここで店をやってて色々聞いたからね」
「いいのか?」
「もちろん。友人には死なれたくないからね」
ラスティは微笑んでそんな風に言った。
「……悪いな」
あの時、偶然ラスティに会って良かったと心から思っていた。もし出会っていなければ、今頃俺はどうしたらいいか分からず途方に暮れるだけだっただろう。
カウンターに腰掛けた俺に、ラスティは「……ベルナードくん」と真剣な声で呼んだ。嫌な予感がして、その先を聞きたくなかったが、俺はラスティを見上げる。
「……アイルーズくんの傷は悪化してる。このままじゃ……持ってひと月だと思う」
ひと月……。
既に心のどこかで分かってはいた。傷は癒えずにイルの身体を蝕んでいる。太陽の瘴気がイルの生命を燃やし尽くすまで、それはもはや時間の問題だ。
「ぼくもしばらく店は休業にして、なにか方法がないか調べてみるよ。アイルーズくんのおじいちゃんとか、他の吸血鬼も探してみる」
「ラスティ……」
いつものように、ラスティはにこりと微笑みを浮かべる。
「それじゃ、時間もないし、向こうの世界の話をしようか」
「……ああ、頼む」
ラスティの話を聞きながら、俺は脳の端がじりじりと焦燥に焼けていくのを感じていた。
――『ブラッディ・ナイトメア-血を灼く光』フラグメント_Nightmare