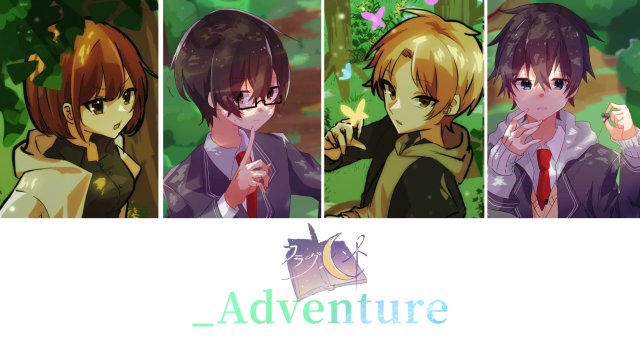蒸し暑い夜の空気が、生ぬるい風に運ばれてくる。
宿のある村に帰る暇もなく、僕たちは森の中で野営をしていた。この森の向こう側には、比較的大きい街がある。かつて人々が暮らしていた街だ。今や魔王軍の残党が住み着いてしまったその街を取り返すことが今回の目的だったけれど、戦闘は長期化している。
僕は立ち上がって野営地を見渡した。僕たちの方が数は圧倒的に少ないけれど、まだこちらの士気は下がっていない。けれどこのままだと、徐々に疲労がでてくるだろう。特に食糧や物資の輸送が妨げられないように注意しなくては……。できれば三日以内、いや、明日にでも決着をつけたい。そんな風に考えていると、背後から足音が聞こえてくる。
振り向いて、そこにラルが立っているのに気づいた。
「……あれ? ラル、どうしたの?」
今回の作戦にはディルとラルも同行している。とはいえ、ディルはやっぱりいつも勝手に行動してばかりなのだけれど。
「ねぇ、ハイト……これ」
ラルはそう言うと、背にまわしていた手をそっと差し出した。その手の中には、花で編んだ冠がある。
「え……僕にくれるの?」
「うん。……この前、私たちの誕生日、お祝いしてくれたから」
ラルは小さな声で言った。――誕生日? 確かに、誕生日が分からないというラルとまおーのために、お祝いをした事があったけれど……。
と、そこまで考えて僕は思い出す。
「あ……今日ってもしかして、僕の誕生日だった?」
「……違った?」
「えーっと……」
最近は戦闘のための日付感覚しかなかったから、改めて日付を数え直してみる。――たしかに今日は、僕の誕生日だった。
「今日であってるよ。あはは、忘れてたんだ……ありがとう」
僕がその花冠を受け取ろうとすると。ラルが背伸びしてひょいっと僕の頭に載せた。
「色々探したけど……ここにはお花くらいしか、なかったから……」
ラルはそんなふうに言って少し悲しそうな顔をした。
ああそうか、と僕は気づく。……ここでの戦いの合間に、僕の誕生日の贈り物になりそうなものを探してくれてたんだ。花だって、この森の中で探すのは大変だったはずなのに……。
「ううん、とっても嬉しいよ、ありがとうラル」
少しかがんでラルに笑いかけると、恥ずかしそうに目をそらす。
――まさか、ラルが僕の誕生日を祝ってくれるなんて思いもしなかった。
「……お誕生日、おめでとう」
いつか僕がラルに伝えたように、ラルはそう言って小さく微笑んだ。
「……うん、ありがとう!」
◆
「ちゃんと渡せたよ、ディル……」
わたしは野営の灯りから離れて、森の暗がりの方へ小走りで進んだ。
その木の幹により掛かるようにして、ディルが立っている。
「……そうか」
「ディルも、ありがとう。お花集めるの、手伝ってくれて」
「…………」
わたしだけじゃ今日までに間に合うか分からなくて困っていたら、ディルも花を集めるのを手伝ってくれた。その事は黙っていろと言われたからハイトには言わなかったけれど、本当はあの花冠は、わたしだけからの贈り物じゃない。
ディルとわたし、ふたりからの贈り物なんだ。
「ねぇディル、……わたしね、誕生日が大事なの、良く分からなかったの」
ディルは返事をしないけれど、話を聞いてくれているのはわかるから、わたしは木の幹に寄りかかって座り込んで続ける。
わたしは自分の誕生日なんて知らなかったし、お祝いされたことなかったから。
「でも、ハイトはわたしのためにお祝いしてくれて……。生まれた日を祝うのはね、その人に出会えたことに感謝するためなんだ、ってハイトは教えてくれたの。だからね、わたしもディルの誕生日お祝いしたいって思ったんだ、けど……」
それに今日、ハイトに花冠をわたして、喜んでもらえて。なんだか少し、それが嬉しかった。
ディルは誕生日を教えてくれないけど、やっぱりわたしもディルの誕生日をお祝いしたい。
そんな風に思いながらディルの顔を見上げると、ディルはしばらくしてから小さく呟いた。
「……そのうちな」
「――ほんとっ?」
わたしは思わず立ち上がって、ディルの顔をまじまじと見つめる。
「……約束だよっ!」
ディルは返事をしないけど、それはきっと約束をしてくれたってことだよね。
今はまだ、お祝いするってどういうふうにやったらいいのか、よくわからないけど……、いつか少しずつお祝いの仕方も勉強して、またこの先も、何回もみんなの誕生日を……いつかディルの誕生日を、お祝いできたらいいな。
そう思いながら、その日もディルと眠りについて、……食べられないくらい大きなケーキを、みんなにプレゼントする夢をみた。
――『戦場の誕生日』フラグメント_Ray