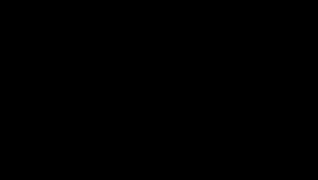◆
庭中を埋め尽くす山茶花の赤が狂い咲く。くらくらするような甘い香りが漂って、仄かな灯籠に照らされた池の汀に、あの子が立っている……。
思わず名前を呼ぼうとして、――夢から覚めた。
ぱちっと、目が合う。
「おはよう、ハイト」
「おっ……おはよう、まおー」
起きたら眼の前にまおーがいるというのは心臓に悪いのでやめてほしいけれど、もはやいつものことだ。夢の残滓はすぐに消えて、僕はベッドから身を起こした。
「朝からどうしたの?」
「ハイトにお願いがあってね〜」
「うん、嫌な予感がするね」
まおーは返事をせずニコニコしている。こういう時はたいてい、厄介事を持ってくるのだということを嫌と言うほどよく知っている。
案の定というか、なんというか。
「ルティがここ数ヶ月帰って来ないんだよ。多分どっかで昼寝でもしてるんだろうけど、連れて帰ってきてくれない?」
まおーの口から飛び出したのはそんな「お願い」だった。
「……え? ルティを探すの?」
「そう」
「えーと、どの辺にいそう、とか……そういうのは?」
「さあ。ティスティアの森の奥かもしれないし、レビ砂漠かもしれないね?」
ぼくはしばし考えた。嫌な予感は的中する。当然のように。
「……つまり、大陸のどこかにいるルティを見つけろって事?」
まおーは満面の笑みで頷いた。
「じゃ、よろしく〜!」
「あ、ちょっと!?」
そそくさと窓から飛び出していくまおーに、伸ばしかけた手は宙に浮かんだ。
「……また無茶振りを……」
今回も、かなり骨が折れそうだなぁと、僕は肩を落としてはためくカーテンを眺めた。
◆
僕たちはいつからか、「まおー軍」なんて呼ばれるようになっていた。
まおー……、赤髪の少年の姿をした魔族。本人が頑なに「まおー」としか名乗らないので、みんなそう呼んでいる。
本当の名前とか謎めいた素性が気になっていた時もあったけど、今はもうまおーはまおーということで慣れてしまった。
何十年も前のことになるけれど、人間の暮らすこの大陸と、魔族の暮らす魔界との間を隔てていた《扉》が開かれ、かつて世界は惨い侵略に蹂躙された。
大陸中は傷つき、美しい街は破壊され、たくさんの人々が殺された。――そんな時、魔族にも関わらず、魔王の侵略軍から離反して人間に味方し戦った者たちがいた。その中心となったのは一人の少年であり……果てには再び《扉》を閉めて世界を救ってしまった。つまりそれが、まおーだったわけだ。
それからも太陽大陸に残された魔族と人間との調和のために、まおーと僕たちは戦い続けている。そんな僕たちに従う者が勝手に増えていった結果、いつの間にかまおー軍と呼ばれる謎の組織の規模は大きくなり、大陸中にその名が知られるようになった。気づけば僕も、まおー軍の幹部とか呼ばれる存在になってしまった。
でもやっぱり僕としては、「僕たち」は「まおー軍」ってより、あの頃のままだって気がする。
今と変わらずめちゃくちゃだったまおーと一緒に、ベル、ルティ、ディルとラルとたった六人で、何千何万の魔王軍を相手に戦っていたあの日々。
仲間と言うにはちぐはぐで、チームと呼ぶには支離滅裂。……ベルとディルが大喧嘩をして、一時はどうなることかと思ったこともあったっけ。みんなはそれぞれ好き勝手、自分の敵と自分のやり方で戦っていただけだった。
でも、確かに僕たちは共に戦った。今思うと、ちょっと信じられないけど。
そしてあの頃――誰よりも弱く何も持たず、剣の握り方すら知らなかった僕に生き延びるチャンスを与えてくれたのは、あの時出会ったまおーであり、そして、なにより、ルティだった。
◆
「さて、ルティがいそうな場所かぁ」
と、僕らの拠点であるまおー城から空へ飛び出して、僕は塔都を見渡した。
ここは大陸の中心――空の彼方にどこまでも伸びる、てっぺんのない不思議な塔の周りに広がる都だ。それで塔都と呼ばれている。戦禍を乗り越えた人々たちの復興の拠点として、多くの人や物が集まる世界の中心地となった場所だった。
「まおーが見つけられないんじゃなぁ……」
とりあえず、レアを呼び寄せることにする。
僕の合図に、レアはすぐにどこからともなく飛来してきた。濡れたように黒い翼を持つ鳥で、黒鴉《ネヴィ》という魔族の者だ。
今では千羽近い黒鴉が僕の指示で動き、大陸中で情報収集をしている。レアはその中心的な存在で、僕と他の黒鴉たちとの連絡係となっているのだった。
「ルティを見かけなかった?」
「最後に見たのは二ヶ月前よ」
「それはどこで?」
「塔都を出ていくところ」
レアは翼をはためかせる。黒い嘴が空の彼方を指した。
「東へ行ったわ」
「おお、それは手がかりだね、助かるよ」
とはいえ行き先がわからない以上、今もルティが塔都より東側にいる保証もない。
「ルティス様を探しているのね? 協力するわ」
「ありがとう、よろしくね」
レアは言葉少なにひらりと身を翻して旋回してから、上空へ飛び去っていった。
大陸中に散らばるレアたち黒鴉がいれば、随分心強い。
「……東かぁ」
他に手がかりと言えばここ二ヶ月、黒鴉たちがルティを見かけていないということがヒントかもしれない。つまり、空からでは見えない場所にいるかもしれないということだ。
「……って言ったって、そんなところいくらでもあるんだよね」
どうも途方もなさそうな予感がして、僕は一旦青空を見上げてぼんやりしてしまった。 さて、どこから手を付けようか。
◆
魔力探知をしながら大陸中をひたすら飛び回った話をしてもいいけれど、結果から言うと何週間にもわたる捜索も全く無駄になった。もし仮に僕の伝記が書かれることがあれば、割愛は免れないであろう空虚な数週間を過ごしてしまった。
「……ってわけで、ルティを探してるんだけど、心当たりはない?」
「――はぁ? この大陸のどっかにいるルティスを探せって?」
僕の問いかけに思いっきり苦い顔をするのは、同じ「まおー軍幹部」……というか、僕たちの仲間のベルナードだ。
最近、何をしているのか僕もよく知らないけど、ベルはほとんどまおー城にはいない。ルティを探して世界中を飛び回っていたら、偶然マグフィカ辺境の荒野でベルの魔力を感じたので、会ってみることにした。
「そういうこと。ルティのことだから別に心配はしてないけど……さっぱり見つからないんだよね」
「まためちゃくちゃ言ってるわけだ、あのガキ」
「あーあ、いいの? まおーをガキ呼ばわりして。また怒られるよ?」
「いいだろ別に……見るからにガキなんだからさ」
荒野の夜は静かで、話す声が響く他には風の音しかない。時折、砂ぼこりが舞い上がる周りには荒涼とした風景が広がるだけだが、わずかに魔物の気配が残っている。ベルも一応、まおー軍の一員としての仕事をしているみたいだ。まあ、僕みたいにまおーから何かいいつけられているのかもしれないけど。
「んー、ルティスか……そうだな……《零の海》には行ったか?」
「零の海って……ああ、あそこ?」
ベルは顎に手を当てて、記憶を探るように斜め上を見る。
「かなり昔だけどな……二十年くらい前だったか。ルティスにあの辺りで会ったことあるぞ。あの辺は魔力が不安定で、遠くからだと気配を探りにくいだろう。あの時は俺も偶然だったが……、連れて帰ったから憶えてる」
「おお……! めちゃくちゃ有力情報じゃん!」
思わず疲れも忘れて飛び跳ねたくなった。ようやく光が見えてきた。
確かにあそこは、大気の魔力が不安定に歪んでいる。魔法によって情報を連絡する黒鴉たちの情報網も、あのあたりに関しては弱点だ。可能性は高い。
「そっかあ、零の海か……思いつかなかったな」
「とはいえ、あれもなかなか広いし……見て回るのも大変だろうけどよ。誰かさんのせいでな」
「はは……まあそれに関しては、誰かさんのおかげってのもあるしね。三日もあればかなりじっくり探せるんじゃないかな。とにかくありがとうベル。助かったよ」
「どういたしまして」
ひらひらと手を振るベルに別れを告げ、僕はさっそく大陸南東の《零の海》へ向かうことにする。
何はともあれ、ベルも元気そうでよかった。ルティが見つかったら、改めてお礼を言いに来よう。と、僕は荒野を後にした。
◆
ようやくルティの背中を見つけた時には、探し始めてから三週間が経っていた。ちょっと意外だったのは、その時ルティが砂浜に立って、海の方を見ていたことだった。眠っていたわけではなかったのか、ちょうど目を覚ましたところだったのか。
「やっと見つけた……」
白い砂浜に降り立って、僕はルティの隣まで少し歩いた。さらさらと靴の裏で砂が崩れる。真昼の陽の光に照らし出されて、海は眩しく碧く輝いていた。
そして零の海は、大陸を囲う普通の海とは違って、その水面からきらきらと粒子が舞い上がってくるのが見られる。
「なにしてるの? こんなところで」
「……ここ、懐かしいから」
そう返すと、ふわぁ、とルティは海を見たままあくびをした。金色の髪が風に吹かれて、舞い上がる。きらきらと輝いた。その肩にはいつものようにうさみが乗っている……。なんとなく、目が合うような、合わないような……僕の方を見ているような、いないような……。思わずじっとみつめていると、くるりとルティは僕の方を向いた。
「探しにこいって、まおーに言われた?」
「あ、そうそう。けど、ずいぶん時間がかかっちゃったよ……ずっとここにいたの?」
「……この辺り、よく眠れるから、寝過ぎちゃうんだよねぇ」
つまり、二カ月近く……? でもまあ、ルティならあり得るんだよなあ、と思わず苦笑してしまう。
「まったくもう。変なところで寝たらだめだってば。……て言っても、ルティなら危ないとかもないしなあ……あー、ほら、風邪とかひくかもしれないし?」
「うーん……ひいたことないけど」
「だよねぇ……」
寝起きらしいルティはぼんやりしている。まあ、寝起きじゃなくても大体ぼんやりのんびりしてるのがルティなんだけど。
ルティがまた海の方に視線を戻すのに倣って、僕も久しぶりに訪れたこの場所の景色を、懐かしい思いで眺める。
零の海は、――本来、存在しなかった海だ。
かつて、《扉》に最も近く位置し、そして大陸で最も栄えていた、レーヴェという国があった。しかし《扉》が開かれてから一帯は魔族との最前線となり、地獄のような激戦地と化した。
そして熾烈な戦闘の末に、最後には大地ごと消滅した。
大陸の南東は大きく欠け、そこに海の水が流れ込んで湾ができた。それが《零の海》……当時の巨大な魔力の残滓が、いまだ周囲の魔力場を不安定にし、粒子をきらめかせる、どこか美しい滅びの海だ。
「帰ろうか、ハイト」
「そうだね。――というか、次遠くに出かけるときは誰かに言ってからにしてよね?」
「うーん、まぁ、気が向いたらね」
「……き、気が向いたらかぁ。……大変だったんだよ?」
「それはごめんね」
ルティは……昔から変わらない。けれど、僕に一番最初に生きる術を教えてくれた《あの人》が――再び、長い眠りから目を覚ます日が来るんだろうか。
僕たちは空へ舞い上がる。輝く海を突っ切って、塔都への帰り道をのんびりと辿った。
――『滅びの傷痕』フラグメント_Ray