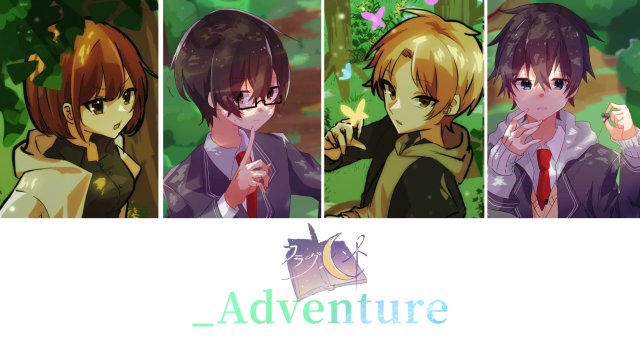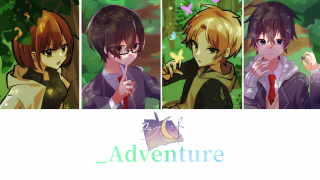『二人は出逢う。終わらない夜に、絶望の傷痕に、月の光が差す頃に』
◇
俺は、森の深い闇の中を駆けていた。
日の出までどのくらいあるだろう。いつまでも夜は明けず、暗闇が無限に続くような気がしてならない。
無意識に何度も何度も、振り返ってしまう。木の陰から、葉の隙間から、あいつの金色の瞳が俺を見ているような気がして。
そんな自分に気が付いて、苛立ちに舌打ちする。
俺があいつの言うとおりに異世界人を召還し、あいつはその異世界人を鍵として《扉》を開けた……魔界はその外にあった世界へとつながり……そして、俺は、魔界から逃げ出した。
ようやく、逃げられる。そう思っていた。あいつの言うことを聞いて、異世界人を召還したのも……全部そのためだった。扉を開けて、その先にあるという、別の世界へ行けば。あいつから離れられると。あの闇に閉ざされた牢獄の世界を、抜け出せると。
――そう思っていた、それなのに。
どこまで行っても、ずっとあいつの影がちらつく。囁く声が風に混ざる。俺の名前を呼ぶあの凍るような声が止まない。振り払っても振り払っても、悪夢がずっと地の底へと引きずり込んでいく……。
右腕から血が滴っていた。痺れて感覚がない。治癒魔法はあまり得意とは言えなかった。傷がなかなかふさがらず、血が流れて冷たくなっていく。
魔王軍はこの大陸を好き勝手に侵略しているらしいが、どうでも良かった。問題は軍の幹部たちが俺を追ってくることだ。あいつに命じられているらしい。――先ほどもそのうちのひとりと交戦になり、俺はろくに対抗もできずに逃げてきた。それですら、命からがらだ。
俺だってそれなりの鍛錬は積んできた――そこらの一般的な魔族相手なら、早々敗けることもないだろう。だが、魔界で最も強いと言われる軍幹部となれば格が違いすぎる。俺はあいつの言いつけに従ってずっと召喚魔術の研究ばかりしてきたので、戦闘魔術では到底かなわなかった。
いつも逃げてばかりだ。
あいつを殺す事を……心の奥底に誓いながら、それができずに、どれだけあがいても些細な反逆すら果たせずに。逃げて、逃げて、逃げて、それでも――逃げられない。
ふらつく足が、地面の石につまずいた。俺はそのまま地面に肩からぶつかって、傷を貫く痛みに漏れそうになる声を殺した。少しだけ……休もうか、とそのまま俺は木の陰にうずくまる。
「お前は逃げられないよ、ラズ」
声が聞こえた気がして、肩がビクッと震える。咄嗟に顔を上げ、周囲を見回すが、誰の姿もない。どこまでも暗い森に、月光が差しているだけだ。
不意に、意味もなく泣きたくなった。俺は影の中に深く身を沈める。こうすれば、大抵の生き物には見つからず身を隠すことができる。
俺はぼんやりと考えている。《異世界》について……。ここではない世界。俺が召喚した、あの二人の少女たちが生きていたという世界だ。それは魔界と扉で繋がっていたこの大陸とも違う。もっと遠く別の場所にある、完全に切り離された異世界。
俺が成功させたのは、その異世界の者をこちらに転移させる《世界渡しの召喚》だけだ。結局、元に戻すこともできなかった。旧時代の文献には、ごくわずかに《世界渡り》についての記述もあったが、それこそ、伝説のようなものだ。もしかしたら、実在はしないおとぎ話に過ぎないのかもしれない。
――だが、もしも、違う世界にいけたら。ここじゃない、遠くへ、あいつのいない世界に行けたら。
なんて……。
そうやって逃げ続けても、何の意味もないことにはとっくに気づいている……。
浅い眠りにまどろんでいると、耳元でハッキリと声がした。
「ラズ、お前には才能がある」
周囲が塗りつぶしたような暗闇に閉ざされる。
「人を殺し、全てを壊す才能だ。まぁ、お前にはそれ以外に何の価値もないけれどね……だから僕がお前に生きる意味を与えてやるよ……」
何度も何度も体を傷つけられ、それを癒やされ、傷痕と呪いのような言葉だけが残る。その繰り返しの中で、俺は生きながらえてきた。
俺の生きる意味、殺す以外に価値のない命、あいつが俺に与える意味……。俺は……俺が生きられるのは――。いや、違う。
冷たい指が俺の頬を這う。ぞっとするほど明瞭な感覚を振り払いたくてもがいた。
だが夢から醒めることができない。
「お前は僕のところでしか生きられないよ、ラズ」
――違う!!
叫びたくても声が出ない。首が絞められたように、息ができない。
違う――、……俺は……――。違うなら……。
――違うなら、何だというのだろう……。
その時、
なにかが、頬に触れた。
柔らかく、冷たい。けれど不思議と、怖くはなかった。
霧のようにすべてが消え去り、目を開ける。
ぼやけた視界で、深い赤色の瞳が、俺をみていた。
息を呑む。

そこには、まだ4、5歳くらいの、幼い人族の子供が居た。
泥だらけの顔で、俺の頬に、手を伸ばしていた。
――気が付かなかった。こんなに近づかれるまで。
「……ないてるの……?」
はっと、俺は自分の頬にふれる。
血と泥に混じって、確かに濡れていた。
子供はおろおろと、困ったように俺の目を見返す。ぼろぼろの布をかぶるように着て、むき出しの膝が擦り切れている。
「……いたいの? けがしてるの?」
俺は頬を拭いながら、妙な気分だった。この子供が触れるまで、俺はこいつの存在に気が付かなかった。けれど、目が覚めても、体が動かなかった。反射的に攻撃して殺してしまってもおかしくなかったはずなのに、どこまでも、今も……穏やかだった。
「……なにしてんだ、こんなところで」
「えっと……」
俺は立ち上がる気も失せて、座ったまま視線を合わせた。
「……おいていかれたの」
「誰に」
「むらのひとたちに、つれてこられて、それで……」
ここは魔物が跋扈する夜の森の中だ。
おそらく……捨てられたのだろう。人族にしては、赤い眼が特徴的だ。そのせいだろうか。あるいは、暮らす村が魔王軍に襲われたのか?
いずれにせよ、この子供に迎えは来ないことは確かだった。この子供が辿る運命は、獣に喰われるか、飢えて死ぬか……そのどちらかだろう。
俺は立ち上がった。俺にはどうすることもできない。拾ってはいられないし、そういった理不尽などこの世には溢れかえっている。今、いったいどれだけの人族が何の罪もなく殺されている事だろう。――俺が、扉の鍵となる異世界人を召還したせいで。
そう思った瞬間、身がすくんだ。
「ご、ごめんね、おこしちゃって……」
見下ろすと赤い瞳は、俺を見上げたせいで月明かりを反射していた。思わず、目をそらす。
「でも、けが……だいじょうぶかなって、おもって、それに、ないてたから……」
無性に苛立ちが湧きあがった。無様な姿を見られたこともそうだが……。
こいつは、まるで自分のことを顧みていない。
俺なんかよりも、自分のほうがどう考えても危険な状況のはずなのに。何の力も持たず死を待つだけのただの子供が、俺を心配するなどおかしいにもほどがある。それに……俺は、魔族だ。今、大陸中を侵略し、虐殺を繰り返している魔族。一目でわかるはずなのに。なぜ、こいつは恐れない?
「……いたいの? くるしいの?」
「違う」
気にかかることはもうひとつある。なぜこの子供は、俺の魔術による潜伏を破って近づけたのか。それを頭の片隅で考えていた。この大陸に暮らす人族も魔法を使えるとは聞いたことはあるが、魔族のそれほど優れたものではないらしい。
なら……この子供は……。
ふと、右腕の痛みが軽くなっていることに気が付いた。軽く動かしてみる。傷口を見てみると、眠る前よりも塞がっていた。感覚も戻っている。ただ少し眠っただけでここまで傷が癒えるはずはない。
……まさか。
「……だいじょうぶ?」
そんな風に首を傾げる子供を見下ろして、俺は考えた。
暗い閃きが頭をよぎる。
この子供を、うまく使えないだろうか、と。
俺は、ずっと揺れ動いていた。あいつを絶対に殺すというたったひとつの意志。だが現実にはそれが不可能で、逃げることしかできなかった。殺したい。逃げたい……矛盾し、揺れ動き、引き裂かれそうで――それでも覚悟が足りなかった。
あの日もそうだった……逃げることも、殺すこともできず、ただ見ているしかできなかった……。
この先もずっとそうなのか?
何千回も問い直して、覚悟を決めたつもりで、それなのに揺らいでいる。
変えられないなら、俺の生きる意味は一生、あいつの手の中だ。
あいつを殺すためなら、なんだってしてやる。そのためなら、なんだって、利用できるものは利用する。それだけの覚悟が必要で、最初から、そのために選んだはずの道だった。なのに、俺は弱すぎて――ただ逃げるために殺し続けるなんて、最悪だ。
俺は子供に向き直った。
少し考えたが、結局は口を突いて出たのは単純な言葉だった。
「俺と来るか?」
「え……?」
「お前には迎えなんて……来ない」
俺はじっと見下ろす。子供はぽかーんと俺を見つめていた。
なんだか急にばかばかしくなって、身を翻す。
「自分で決めろ。俺はもう行く」
「あ。あ。えっと、えっと――いく!」
後ろから慌てたような足音が聞こえた。これでもう後には引けない、と思うと急に気怠さが襲ってきた。
どう育てればうまく使えるだろう。と考えるが、頭が回らない。そもそも、子供の育て方すら全く知らなかった。人族は魔族に比べて成長が早く、寿命も短いらしいが……。
「あの……その……おなまえは?」
俺はその瞬間、自分の選択を早くも後悔した。考えてみれば、他者と行動を共にするなんて、反吐が出そうだった。しかもそれが幼い子供ときたら、なおさらだ。
答えずにしばらくそのまま、森を歩いた。子供は足が遅く、なんども木の根や泥に足を取られて転びそうになっていた。
何度も何度も、やっぱり置いていってしまうかと足を速めかけた。だが後ろから追いかけてくる足音が結局は俺の歩みを遅くさせる。
「……ディル」
そう口にすると、しばらく間があいて、「え?」と間抜けな声がした。
「名前だ」
「ディ、ディルさん……?」
「ディルでいい」
わたしは……と、背後から聞こえる言葉を遮った。
「お前の名前はいい」
「え……? いい……?」
「もう必要ない。あとで俺がつけてやる」
そのほうがいい。
お前の名前を……俺が汚すことがないように。
手の甲が疼く。
気づけば爪を立てて、そこを覆っていた包帯がないことに気づいた。刻まれた刻印が、俺の頭を支配する。後ろをおぼつかなくついてくる存在のことを考えれば考えるほど、どうしても、かつての俺に重なる。
やがて手の甲の疼きは焼けるほどの熱さに変わり、耐えられなくなった。俺は服の中からナイフを抜き取って、左の甲を貫いた。傷が重なる。
血が溢れて、その痛みが、熱さをごまかす。
「ど、どうしたのっ!? いたいよ……」
俺は無視して歩く。ナイフをしまう。
「きれいな、模様なのに……」
俺の足が止まった。ひどく心の底が冷えた。足元に子供がぶつかって、反射的に蹴り飛ばしそうになるのを抑える。
「黙れ。もう二度と見るな」
「ご、ごめんなさい……」
吐き捨ててまた歩き始める。
血が滴って、その刻印をほんの少しの間、隠してくれる。
俺はあいつを殺す。
全てを、あらゆるものを犠牲にしてでも。正しさも、救いもどこにもない。ただ、ここにあるのは犯し続ける罪と、罰のように繰り返される呪いだけだ。
「……お前の名前は」
「……?」
「シュトラルカだ」
シュトラルカ、と子供は呟く。
「いいなまえ……だね。ありがとう。ディル……?」
疲れたような息のはざまで、とぎれとぎれに聞こえてくる。
こいつは、いつまで俺の傍にいるんだろう。すぐに死ぬかもしれない。結局嫌気がさして、見捨てることになるかもしれない。
だが、もし、――いつか。
いつか俺があいつを殺して、この烙印を永遠に消し去る時が来たら。
その時……シュトラルカの本当の名前を、知りたかった。
バカバカしいことに、何故か俺は、あいつを殺したあとのことを考えている。
今までそんなこと、考えたこともなかったのに。
いや、そうだ……俺には未来など、ない。
もう少しで、森を抜ける。
これからどうしようか。俺だって魔王軍に追われている身だ。できるだけ、魔王軍たちの目の届かない場所へ逃げなければ。あいつにだけは絶対に見つからないように。……なんて思いながら、俺の居場所や行動なんて、あいつにはすべて見通されているように思えてならない。今も、どこかで俺の馬鹿げた選択をあざ笑っているような気がした。
「……つき、きれいだね」
……痛いなら、越えればいいはずだ。
シュトラルカ。かつて、あいつが戯れに俺をその名で呼んだ。旧時代の文献に残る、旧い言葉。意味は……《人形》。
俺は覚悟を握りしめる。今にも打ち砕けてしまいそうな心を保って。俺は強くならなければ。たとえどれだけの犠牲を払おうと。どれだけ苦しむことになっても。あいつを殺せるぐらい、もう誰にも奪われないように、強く、それしか。それしか俺には。
「……ああ、そうだな」
流れるように、そう返した。
見上げた月は孤独にうかんで、確かにきれいだと、一体いつぶりかそう思った。
――『孤月のプロローグ』フラグメント_Nightmare